第六回 佐藤鬼房顕彰全国俳句大会嘱目入選句
【 平成25年3月24日〔日〕 於 ・ 塩竈市エスプホール 】
嘱目の部の選考は、全選者が参加しての公開討論を経て、以下のとおり決定しました。

ひとりも死なぬ日のやうに花菜風 仙台市 泉 美智子
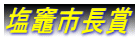
輪郭のおぼろに鯨老いにけり 仙台市 小川真理子

潮の香や在れば一年生なるか 涌谷町 鈴木喜久郎

ふくしまや抗いて種蒔けばこそ 福島市 坂本 豊

第一席 啓蟄や藁にまみれて仔牛立つ 市川市 小林 眸
第二席 輪郭のおぼろに鯨老いにけり 仙台市 小川真理子
第三席 ひとりも死なぬ日のやうに花菜風 仙台市 泉 美智子

第一席 囀りに好きすきすきと囲まるる 一関市 伊東 静枝
第二席 ふくしまや抗いて種蒔けばこそ 福島市 坂本 豊
第三席 「ご自由に」と仮設八百屋の猫柳 多賀城市 黒田 利男

第一席 ふくしまや抗いて種蒔けばこそ 福島市 坂本 豊
第二席 潮の香や在れば一年生なるか 涌谷町 鈴木喜久郎
第三席 みな祖母の茶飲友達つくしんぼ 仙台市 山内 栄子
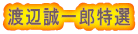
第一席 ひとりも死なぬ日のやうに花菜風 仙台市 泉 美智子
第二席 三月の青き魚がふり返る 仙台市 水月 りの
第三席 桜咲く象の頭の中を思ひ 大阪市 上野まさい

第一席 潮の香や在れば一年生なるか 涌谷町 鈴木喜久郎
第二席 鳰よまた三月十一日がくる 青森市 佐々木とみ子
第三席 苜蓿地に湧き出でよ荒蝦夷 東京都 瀬古 篤丸
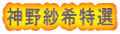
第一席 三月の青き魚がふり返る 仙台市 水月 りの
第二席 桜咲く象の頭の中を思ひ 大阪市 上野まさい
第三席 姫皮を炊く鬼房の黄泉苞苴に 石巻市 土屋 遊蛍

第一席 ありし日の人と見てゐる桜かな 栃木市 鯉沼 桂子
第二席 海へ還りし抽斗の桜貝 多賀城市 酒井美代子
第三席 ぞつくりと土筆の生れる更地かな 利府町 大友セツノ

第一席 余寒なほ塩土老翁深眠り 角田市 鈴木 三山
第二席 涅槃西風藻塩の竈の覚かな 塩竈市 池田智恵子
第三席 涅槃会の海にひとしほ海猫の声 仙台市 浪山 克彦
 
開会式 嘱目の部公開選考会
第六回佐藤鬼房顕彰全国俳句大会参加記①
初めての「小熊座」
瀬 古 篤 丸
歌枕の地、塩竈。しかし、東北本線塩竈駅前は人口減少の例にもれない地方都市のそ
れであった。例年ならば、海の見える会場だったと聞き、残念に思いつつ会場となるホー
ルのエレベーターを降りたとたん、目に飛び込んできたのは、鬼房の自筆の短冊、色紙。
今、塩竈にいて鬼房の字で、鬼房の句を脳裡に刻む。その字は伸びやかでいて、癖があ
り、俗を越えたユーモアがあり、飽きない字。一遍に魅了され、海の見えない残念さが吹っ
飛んだ。
三月二十四日、塩竈で開催された、「第六回佐藤鬼房顕彰全国俳句大会」は、ジュニア
の人たちの入選句の発表から始まり、小学生から高校生までの入賞者が壇上に呼ばれ
た。
奨励賞は〈花びらは帰ってこない桜の木〉 小学六年生の佐藤優太郎くんが賞状を受け
取るために、壇上にいた。十二歳の少年は、まだ小さく色が白く、手を両脇にきちんと伸ば
して立っている。初々しさと育ちの良さと、「桜にはもどらない……」と感じた無常をその小
さな身体で受けとめているような、現代っ子にない風情がある。「東北だねえ」と、勝手にデ
ィスカバージャパン的なステレオタイプな感慨に耽ってしまった。今日の俳句大会に来てよ
かった。
「鬼房とみちのく」と題したシンポジウムは、関西人でフランスかぶれの私は、今さらだ
が、「周辺と中央」という問題を再認識させられた。「みちのく」を強く意識しているのは、東
北の人たちである。そして「みちのく」人であることを誇りとしている。それはこの度の地震・
津波のずっと以前から、アテルイの敗北に、義経の悲劇に根差し、現代社会においてもな
お続く抑圧の歴史を経て、一種の「敗者の美学」なるものが「みちのく」の人たちの中に形
成されているからだろう。当日参加されていた、歌人の佐藤通雅氏曰く、「鬼房の低いもの
へのまなざし、アテルイの精神、惨めだが生きる力を溜めている人……」と。鬼房と東北の
風土性である。
「みちのく」の秘めたる力を信じたい。
宮城県に来るには、福島県を通らなければならない。福島県の山河は、まだ春の入口で
あったけれど、その美しさは知れた。それなのに人の住めなくなったところがあり、産物は
摂取制限となり、風評被害はおさまらない。こうした状況に東北からもっと強い不満の声が
上がらないのが不思議だ……フランスかぶれの私には、「ノン」と言うことが存在証明であ
るというようなフランス人と日々向き合っているが故により強くそう思うのだろう。
幾たびか死を浴び返し拘尾草
第六回鬼房奨励賞の武良竜彦氏の句。拘尾草のたよりなげだが、〝浴び返す〞ごとく
元にもどる姿は、秘めたる力だろうか。
とまれ、日本社会のシステムとして、「中央を支える周辺」というものがあるのは事実だ。
原発はそのシンボルとしてあるかのようだ。震災後ほんの少しの間このシステムは、変更
可能かと思わせたが、やはり揺るがないようだ。「周辺」は、依然としてリスクを負い、まや
かしの利益を得ては、「中央」に奉仕する。東京という中心からは周辺である東北の現実
は見えない。我々東京に住む人間は、「中央」にいるという意識がない。
この度の俳句大会に参加して、「小熊座」の同人たちの深い人間関係の話の端々から、
「中央を向いている人……」「中央に出て行く人……」「中央を目指す人……」という、〝中
央〞という表現がたびたび口をついて出てくることに、驚きと納得を禁じえなかった。
鬼房の句の「みちのく」性は主体性をもっている。単なる地方性ではなく、普遍性を持って
いる。これが、シンポジウムの結論だったかと思う。しかし、「力は秘められたまま」かもし
れない。
ひとりも死なぬ日のやうに花菜風
当日の嘱目の部の公開選考により、鬼房奨励賞に選ばれた仙台市・泉美智子さんの句
だ。手作りで進められるゆっくりとした大会の進行に身を委ね、「みちのく」の俳句大会で詠
まれる句の問うている大きな意味を考える時間が流れた。
結局、塩竈の海も神社も次回のお楽しみとなった。
第六回佐藤鬼房顕彰全国俳句大会参加記②
小熊座というコミュニティの輝き ――佐藤鬼房顕彰全国俳句大会
武 良 竜 彦
この日の大会をたくさんの同人・誌友の方たちが笑顔で運営されている姿を見て、人探
しで訪ねた福島の各地で目撃した、ボランティアの人たちの笑顔を思い出しました。過酷な
被災体験をされた方も多いはずです。
そんな中、死の恐怖と直面された同人の小笠原弘子さんと、震災後初めてお会いするこ
とができて、涙が込み上げました。小笠原さんは、手紙に「俳句に救われました」と書いて
いらっしゃいました。そのお言葉のように、被災された小熊座同人たち(未だ仮設暮らしの
方もいらっしゃいます)の心を支えたのは俳句であり、小熊座俳句会というコミュニティだっ
たのだと実感しました。
山下祐介氏が『東北発の震災論』で論述した、小単位のコミュニティの支援なしには、被
災者の心の復興は不可能だったという言葉通り、この日私はその輝きを目撃しました。
大会は中核に「鬼房俳句とみちのく」というシンポジウムが置かれていました。鬼房先生
は陸奥の「風土性や土俗性」を題材として詠んだだけの俳句を「観光俳句」と批判された
(矢本大雪氏の言葉)といいます。陸奥という風土を詠むことが目的ではなく、この社会と
時代に生きた証として、陸奥の風土性と同時に、生のリアリティと命の普遍性が造形され
ているのが鬼房俳句であるということでした。それは震災俳句の議論でもあったように、震
災体験を題材として詠むのではなく、被災地に生きて詠んだ証として、俳句がある(高野ム
ツオ主宰の言葉)ということと同じです。私が愛唱する鬼房俳句は次の句です。
観念の死を見届けよ青氷湖 『枯峠』
青氷湖は幼時、鬼房先生が姉と慕った女性が入水した加瀬沼という話もありますが、こ
の「観念」という語の使い方に、鬼房俳句の本質が凝縮されているように感じます。
この「観念」とは人間の生きている証としての想いのすべてです。人の死に際して通常、
身体的、社会的活動の全停止の方が語られ、その人がどんな思いを紡いで生きてきたか
という、内面世界のことが置き去りにされる傾向があります。そうではなく個別的な内面世
界である「観念の死」が「見届け」られて、人は初めて「人としての死」死ぬのです。
金子兜太は鬼房俳句の業績を、生活の中で生起する「寂の思想」という「観念」を、俳句
に刻印したことだと、過去の鬼房顕彰全国俳句大会の記念講演で述べています。そういう
意味でも、それまでの俳句にはなかったこの俳句の「観念」は、俳句史的な表現の闘いの
言葉としても、私の心を占めています。
私事ですがこの大会で、正木ゆう子先生と渡辺誠一郎編集長に拙句を二句ずつ選んで
いただき、その上、鬼房奨励賞まで賜り感謝いたします。これまで私は、畏友でもある主
宰の句や故田中哲也氏、同人の方たちの才気あふれる句を鑑賞するだけで満足で、俳句
を作る気持ちはありませんでした。しかし畏友田中哲也氏が急逝し、その心の空白を埋め
るのはやはり俳句しかなく、作句を始めました。
死んでなお人に影ある薄暑なり 渡辺誠一郎
震災の被害や数量ではなく、個別的な死を悼む独自の視座による渡辺氏のこの句や、
同じ熊本県出身の憧憬の人である正木先生の、
やがてわが真中を通る雪解川 正木ゆう子
という生死を超えて身体を透過し浄化するような水の流れの句。このような素晴らしい句を
詠めるようになりたいと願っています。
嘱目の部の公開選句会で議論になった、
ふくしまや抗いて種蒔けばこそ 坂本 豊
について「ふくしま」は今や地名ではないと言って推奨された正木先生の言葉と、福島を詠
み続けられている坂本氏に共感しました。
|