| |
小熊座・月刊
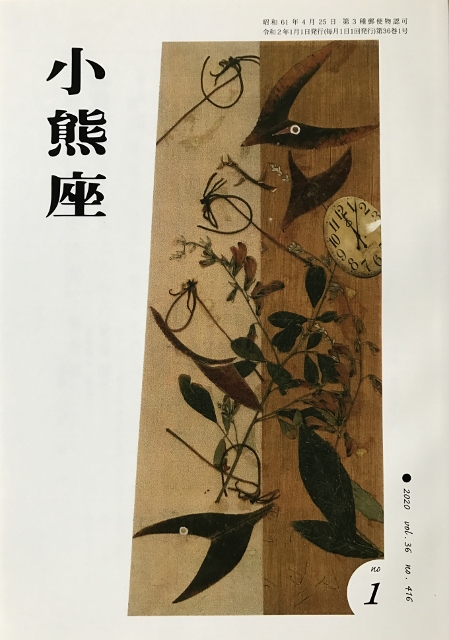 |
鬼房の秀作を読む (114) 2020.vol.36 no.418
追儺豆踏みしばかりに眠られぬ 鬼房
『瀨 頭』(平成四年刊)
難解な言い回しは見当たらず、むしろ平明で透明な句でありながら、謎めいている。それ
が、最初に一読した際の印象だった。裏返せば、この句の魅力ともいえよう。定型のなか
でいて、定型をはみださんばかりの不思議な重々しさがあるのだ。
もっとも心に引っ掛かったのは 「踏みしばかりに」 の告白めいた表現だ。作者の強い思
い、逃れようのない後悔のようなものがにじむ。鬼を追う「追儺豆」だからこそ、そこまで表
現させるのではないか。人が鬼を、追い立てるに投げつける豆。今ではほほえましい節分
の行事だが、その行為の意味を突き詰めていくと、人のさがのような業のような、自分と異
なる存在を攻撃せざるを得ない本能を示唆しているのかも、とふと思い至る。
足裏に残る、小さな豆の冷たくて硬い感触。その生々しい実感は、戦場に転がる弾のよ
うに鈍く光っては、眼裏にいつまでもちらつく。「眠られぬ」に、作者の濃やかな感性と苦悩
の厚みが感じられる。争わずにいられない人間、いや人類の痛みがのしかかり、作者を
眠らせなかったのではないだろうか。
一瞬であっても、追われる〝鬼の側〟へ思いを至らせる感覚。その感覚を持ち得た鬼
房という俳人の、深い人間的な器あってこそ生まれた句だろう。
(大高 翔 「藍花」 )
第十句集『瀬頭』の中の天児抄の一句である。句集『瀬頭』で蛇笏賞を受賞。この受賞は
金子兜太に「佐藤鬼房の受賞が嬉しい……総領をかけていけば、その人らしい俳句の形
姿も、技法も出来上がってくるものだ、ということも。」鬼房の句は難解である。俳句を学ぶ
者として恥を知れと叱られそうだが、あえて恥を晒しておこう。
年が明けると心なしか太陽が強さを増し、春を待つ気持ちが楽しくなる。冬の終わりの追
儺は現在の私達の生活では節分の豆撒きで邪鬼を払う行事としてある。
私の鑑賞力では鬼房の心の奥には入れないと思うが、一般の家庭の「鬼は外 福は内」
と豆を撒く様子に重ねてみようと思う。
鬼房は子煩悩な父親であった。父と遊ぶかに子ども達は豆を撒く光景が見えてくる。家
長として家族の健康と明日からの生活を祈った豆撒きだったが数粒の拾い残しの豆を踏
んだ瞬間心が曇った。撒いた豆は鬼房にとっては神だったのだ。撒いて心が晴れたのに
神を踏んだような畏敬の念に駆られたのであろう。その時俳人「佐藤鬼房」は自身の体へ
の不安、家族、作品への想いがあふれたのではなかったか。追儺の夜は安らかに眠る家
族の顔を見て自身もぐっすり眠りたかったのだ。
(中鉢 陽子)
|
|
|